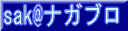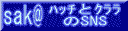お気に入りBlog新着
柴村ってどこ?
また実家で母が怪しいことを言っていました。
柴犬の語源が今の松代の柴(あるいは柴町)だというのです。
そこでWikiPediaで柴犬について調べました。
毛色、大きさなどから「柴」としている説の後に
「ほかに、信州の柴村を起源とする説もある」と書いてあります。
マイナーな説であるにしても
「信州の柴村」がどこのことを言っているのか気になりました
(ただし純粋な信州柴犬は今はいないそうです)。
母の言うとおり今の松代町柴(あるいは柴町)なのか、
それ以外に長野県のどこかに柴という地名があるのか…。
柴犬の語源が今の松代の柴(あるいは柴町)だというのです。
そこでWikiPediaで柴犬について調べました。
毛色、大きさなどから「柴」としている説の後に
「ほかに、信州の柴村を起源とする説もある」と書いてあります。
マイナーな説であるにしても
「信州の柴村」がどこのことを言っているのか気になりました
(ただし純粋な信州柴犬は今はいないそうです)。
母の言うとおり今の松代町柴(あるいは柴町)なのか、
それ以外に長野県のどこかに柴という地名があるのか…。
干支(えと)について
よく十二支の意味で「干支」という言葉を使う方がいます。
私も小中学生くらいの頃はそうでした。
しかし厳密には、
十干(じっかん)と十二支を合わせたものが干支なわけです。
十干の最初は甲(きのえ)で、十二支の最初は子(ね)です。
もっとも最近で甲子だったのは1984年です
(ちなみに甲子園ができたのは、その60年前の1924年)。
簡単に「甲」に「きのえ」と振り仮名を付けましたが
実は、「木・火・土・金・水」×「兄(え)・弟(と)」なわけで、順に
きのえ・きのと・ひのえ・ひのと・つちのえ・…・みずのと
となり、これを漢字「甲・乙・丙・丁・戊・…・癸」
の読みに当てたわけです。
更に付け加えるならば
「干支」の読みも「兄(え)・弟(と)」を当てたのです。
今年は十二支の最初の年ではありますが
十干は戊(つちのえ)ですから、まだ5番目なので
今年を「干支の最初の年」と言うことはできません。
以上、1983年末に先生から聞いた話でした。
風水が流行っている一方で
意外と多くの方が誤解しているようなので
気になって書いてしまいました。
私も小中学生くらいの頃はそうでした。
しかし厳密には、
十干(じっかん)と十二支を合わせたものが干支なわけです。
十干の最初は甲(きのえ)で、十二支の最初は子(ね)です。
もっとも最近で甲子だったのは1984年です
(ちなみに甲子園ができたのは、その60年前の1924年)。
簡単に「甲」に「きのえ」と振り仮名を付けましたが
実は、「木・火・土・金・水」×「兄(え)・弟(と)」なわけで、順に
きのえ・きのと・ひのえ・ひのと・つちのえ・…・みずのと
となり、これを漢字「甲・乙・丙・丁・戊・…・癸」
の読みに当てたわけです。
更に付け加えるならば
「干支」の読みも「兄(え)・弟(と)」を当てたのです。
今年は十二支の最初の年ではありますが
十干は戊(つちのえ)ですから、まだ5番目なので
今年を「干支の最初の年」と言うことはできません。
以上、1983年末に先生から聞いた話でした。
風水が流行っている一方で
意外と多くの方が誤解しているようなので
気になって書いてしまいました。
信濃毎日新聞「真田一族のふるさと」
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
昨日は実家に帰って年越しをしてきました。
「年越し」と言うより「お年取り」という言葉のほうが
ピンと来る私って老人でしょうか? (笑)
実家で酒を飲みながら、色々と松代の話をしました。
実家には色々な本がありました。

「とことん信州松代」には以前に書いた長谷川五作をはじめ
松代にゆかりのある先人がたくさん載っています。
そして↓の本です。

実家に同じ本が2冊あることが判ったので
1冊もらってきました。
これでブログも少しマシになるかも。
今年もよろしくお願いいたします。
昨日は実家に帰って年越しをしてきました。
「年越し」と言うより「お年取り」という言葉のほうが
ピンと来る私って老人でしょうか? (笑)
実家で酒を飲みながら、色々と松代の話をしました。
実家には色々な本がありました。

「とことん信州松代」には以前に書いた長谷川五作をはじめ
松代にゆかりのある先人がたくさん載っています。
そして↓の本です。

実家に同じ本が2冊あることが判ったので
1冊もらってきました。
これでブログも少しマシになるかも。