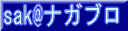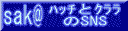お気に入りBlog新着
信濃毎日新聞「真田一族のふるさと」
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
昨日は実家に帰って年越しをしてきました。
「年越し」と言うより「お年取り」という言葉のほうが
ピンと来る私って老人でしょうか? (笑)
実家で酒を飲みながら、色々と松代の話をしました。
実家には色々な本がありました。

「とことん信州松代」には以前に書いた長谷川五作をはじめ
松代にゆかりのある先人がたくさん載っています。
そして↓の本です。

実家に同じ本が2冊あることが判ったので
1冊もらってきました。
これでブログも少しマシになるかも。
今年もよろしくお願いいたします。
昨日は実家に帰って年越しをしてきました。
「年越し」と言うより「お年取り」という言葉のほうが
ピンと来る私って老人でしょうか? (笑)
実家で酒を飲みながら、色々と松代の話をしました。
実家には色々な本がありました。

「とことん信州松代」には以前に書いた長谷川五作をはじめ
松代にゆかりのある先人がたくさん載っています。
そして↓の本です。

実家に同じ本が2冊あることが判ったので
1冊もらってきました。
これでブログも少しマシになるかも。
どこまでが「松代」か

我が家にある数少ない松代に関する本ですが、
この本を読んで初めてあることに気付かされました。
現在の長野市松代町は江戸時代ずっと松代藩で
1871年の廃藩置県により松代県になった数ヵ月後
長野県に併合されるわけですが、それと同時に
松代町、清野村、西条村、東条村、豊栄村、寺尾村、
西寺尾村の1町6村に分けられたのです。
その後、各村が1851~1855年の間に次々と合併するまで
6村には一切「松代」の文字は付かなかったわけです。
という観点で考え直してみると、
「松代大本営」の殆どの施設も、
先日ブログに書いた「六工社」も、
当時は松代ではなかったわけです。
私が生まれたのは松代町が長野市と合併してからなので
自分の育った土地が松代と呼ばれなかった時期があったことに
(小学校の図書館の本に「埴科郡○○村」とあったので
わかっていたことですが、発想の転換をさせられると)
驚きを感じてしまうわけです。
当時の人たちはどう思っていたのかと思わずにはいられません。
“千葉にあるのに東京ディズニーランド”の感覚で、あるいは
関東一円にキャンパスが点在する東京○○大学のように
“松代大本営”だったのか、それとも6村に住んでいた人たちも
「長い間ずっと松代だったんだから、やっぱり松代」だったのか。
富岡日記と乾徳寺
今はどう教えているのか知りませんが
私が中学生の頃は官営富岡製糸場のことを教わる際に
和田英の「富岡日記」についても教えられました。
その和田英が松代出身だとは知っていたものの
横田家出身だと知ったのは最近のこと。
「旧姓横田」と併記してあるのを見てないことは
無いとは思いますが、その横田というのが
あの、横田家住宅の方とは思いもしませんでした。
松代の観光パンフレットに横田家住宅(地図はこちら)の
写真は載っているものの「昔の武家屋敷」という知識だけで
「横田って誰?」という感じで今まで全く知らなかったのです。
(修復工事の最中に何かの用事があって入らせてもらっただけで、
実は工事完成後に入ったことがないのです)。

(上図はインターネット等で調べた情報から私が作成したものですので、
追加情報・誤り等がありましたらご連絡ください)
横田英は富岡製糸場から松代に帰った後、
西条村(にしじょう)六工(ろっく)に創設された
六工社(ろっこうしゃ)製糸場(地図はこちら)に貢献します。

残されているのは看板とこの碑だけで草ボーボー。
六工社の施設は太平洋戦争期の慰安婦問題とも
関係してくるので保存に消極的なのかもしれません。
更に驚いたのは、筝曲八橋流(京都といえば「八ツ橋」
ですが乾いてるほうが元祖で、箏の形をしています)の
真田志んも上図のように横田家にゆかりがあって
和田英とは叔母・姪の関係になるわけです
(緑色が八橋流の伝承経路、叔子で八橋流は途絶)。
和田英は佐久間象山と同じ蓮乗寺に墓所があります。
私が幼い頃に松代で演奏会もあったそうですが
親に「連れてったのになぁ」と言われても
私には記憶にないのか行ってないのかすら判りません。
真田志んは真田勘解由家の菩提寺である
乾徳寺(けんとくじ,地図はこちら)に葬られています。
私が中学生の頃は官営富岡製糸場のことを教わる際に
和田英の「富岡日記」についても教えられました。
その和田英が松代出身だとは知っていたものの
横田家出身だと知ったのは最近のこと。
「旧姓横田」と併記してあるのを見てないことは
無いとは思いますが、その横田というのが
あの、横田家住宅の方とは思いもしませんでした。
松代の観光パンフレットに横田家住宅(地図はこちら)の
写真は載っているものの「昔の武家屋敷」という知識だけで
「横田って誰?」という感じで今まで全く知らなかったのです。
(修復工事の最中に何かの用事があって入らせてもらっただけで、
実は工事完成後に入ったことがないのです)。

(上図はインターネット等で調べた情報から私が作成したものですので、
追加情報・誤り等がありましたらご連絡ください)
横田英は富岡製糸場から松代に帰った後、
西条村(にしじょう)六工(ろっく)に創設された
六工社(ろっこうしゃ)製糸場(地図はこちら)に貢献します。
残されているのは看板とこの碑だけで草ボーボー。
六工社の施設は太平洋戦争期の慰安婦問題とも
関係してくるので保存に消極的なのかもしれません。
更に驚いたのは、筝曲八橋流(京都といえば「八ツ橋」
ですが乾いてるほうが元祖で、箏の形をしています)の
真田志んも上図のように横田家にゆかりがあって
和田英とは叔母・姪の関係になるわけです
(緑色が八橋流の伝承経路、叔子で八橋流は途絶)。
和田英は佐久間象山と同じ蓮乗寺に墓所があります。
私が幼い頃に松代で演奏会もあったそうですが
親に「連れてったのになぁ」と言われても
私には記憶にないのか行ってないのかすら判りません。
真田志んは真田勘解由家の菩提寺である
乾徳寺(けんとくじ,地図はこちら)に葬られています。
Re:【マメ知識】松代町の町名
本来ならば昨日のブログのコメント欄に書くべきことですが
何度も推敲しないと文章を作れない人間なので
改めて本日の日記ぶんに書かせていただきます
(こういうスタイルを今後も取らせていただくと思います)。
昨日はブログ最初の記事からウソ情報を書いてしまいました。
フォローしていただき本当に助かりました。
要するに最初に作ったのが「まち」
その後に作ったのが「ちょう」なんですね。
30年近く思っていた先入観を払拭できました。
期せずして表/裏柴町(この辺り)と柴(この辺り)
の関係も知ることもできました。
どうもありがとうございました。
恥ずかしながら小学生まで「柴」の交差点で
いつも「むらさき」と読んでいました。
何度も推敲しないと文章を作れない人間なので
改めて本日の日記ぶんに書かせていただきます
(こういうスタイルを今後も取らせていただくと思います)。
昨日はブログ最初の記事からウソ情報を書いてしまいました。
フォローしていただき本当に助かりました。
要するに最初に作ったのが「まち」
その後に作ったのが「ちょう」なんですね。
30年近く思っていた先入観を払拭できました。
期せずして表/裏柴町(この辺り)と柴(この辺り)
の関係も知ることもできました。
どうもありがとうございました。
恥ずかしながら小学生まで「柴」の交差点で
いつも「むらさき」と読んでいました。
【マメ知識】松代町の町名
長野市松代町は松代町松代、松代町東条、…
などと細分化されていますが
今回はその中でも松代町松代のお話です。
現在では、郵便を出す際「長野市松代町松代」の後には
番地を書くだけで充分なのですが
他の地域と同様、更に細かい町名があります。
殿町、代官町、紺屋町、馬場町、…と色々あるのですが
とのまち、だいかんちょう、こんやまち、ばばちょう
と「町」の字の読み方が「まち」だったり「ちょう」だったり。
初めての方はおそらく迷われるんじゃないかなぁと思います。
これには実は一般則があるんです。
たいてい「町」の前には職業の名前が付いていますが
それを士農工商のどれに当たるか考えてください。
士であるものは「ちょう」それ以外は「まち」になります。
「馬場町」→「ばばちょう」、「紺屋町」→「こんやまち」
になるわけですね。
でも、お殿様は一番偉いから
「殿町」だけは「とのまち」なんだって。
よくわからない理屈だけど、ちょっとマメ知識でした。
などと細分化されていますが
今回はその中でも松代町松代のお話です。
現在では、郵便を出す際「長野市松代町松代」の後には
番地を書くだけで充分なのですが
他の地域と同様、更に細かい町名があります。
殿町、代官町、紺屋町、馬場町、…と色々あるのですが
とのまち、だいかんちょう、こんやまち、ばばちょう
と「町」の字の読み方が「まち」だったり「ちょう」だったり。
初めての方はおそらく迷われるんじゃないかなぁと思います。
これには実は一般則があるんです。
たいてい「町」の前には職業の名前が付いていますが
それを士農工商のどれに当たるか考えてください。
士であるものは「ちょう」それ以外は「まち」になります。
「馬場町」→「ばばちょう」、「紺屋町」→「こんやまち」
になるわけですね。
でも、お殿様は一番偉いから
「殿町」だけは「とのまち」なんだって。
よくわからない理屈だけど、ちょっとマメ知識でした。