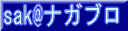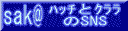お気に入りBlog新着
2007年10月17日
六工社について考察
10月2日のブログを少しだけ考察(というか課題作りです)。
まず、六工社の立地条件について。
「富岡製糸場のあらまし」によれば
1.富岡付近は生糸を作るのに必要な繭が確保できるから。
2.工場建設に必要な広い土地が用意できるから。
3.製糸に必要な水の確保ができるから(鏑川、高田川)。
4.燃料(ねんりょう)の石炭が近くの高崎で採れるから。
5.地元の人たちの協力が得られたから。
が官営工場を富岡に立地した条件だったようですが、
これと比べてみたいと思います。
1.私が生まれた頃も養蚕は残っていました(気象条件がカギ?)。
2.民営だから狭くてもOK?
3.神田川の目の前ですね(水は足りたのかな?)。
4.もしかして山の木を切ってきた???
5.外国人は来ないから関係ないのかな?
疑問符だらけになってしまいました。
色々と調べていたら、pdfファイルが見つかりました。
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/riim/img/img_res/WPNo.19_imai.pdf
ふと思ったのですが、なぜ明治時代には
日本からあんなに生糸が輸出されたのでしょうね。
輸入した国は生糸で何を作ったんでしょう?
今の時代に生きていれば、
自動車や半導体の生産が大事だということはわかりますが
学生時代に社会科が苦手だった私にはどうにも見えてこないです。
確かにシルクは魅力がありますが…。
当たり前すぎることって調べても書いてないものですね。
生糸に代わる材料としてナイロンが開発されましたが
「NYLONを逆に読むとノーリン(農林省)」なんて
高校の先生が冗談を言っていたのを思い出してしまいました。
輸送はどうしていたのでしょうね。
六工社ができたのが1874(明治8)年
長野駅開業は1888(明治21)年
千曲川で運んでいたのでしょうか?
そうそう、製糸といえば、
当然こういう話題も関係してきますね。
「がむがゆく」 10月13日
まず、六工社の立地条件について。
「富岡製糸場のあらまし」によれば
1.富岡付近は生糸を作るのに必要な繭が確保できるから。
2.工場建設に必要な広い土地が用意できるから。
3.製糸に必要な水の確保ができるから(鏑川、高田川)。
4.燃料(ねんりょう)の石炭が近くの高崎で採れるから。
5.地元の人たちの協力が得られたから。
が官営工場を富岡に立地した条件だったようですが、
これと比べてみたいと思います。
1.私が生まれた頃も養蚕は残っていました(気象条件がカギ?)。
2.民営だから狭くてもOK?
3.神田川の目の前ですね(水は足りたのかな?)。
4.もしかして山の木を切ってきた???
5.外国人は来ないから関係ないのかな?
疑問符だらけになってしまいました。
色々と調べていたら、pdfファイルが見つかりました。
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/riim/img/img_res/WPNo.19_imai.pdf
ふと思ったのですが、なぜ明治時代には
日本からあんなに生糸が輸出されたのでしょうね。
輸入した国は生糸で何を作ったんでしょう?
今の時代に生きていれば、
自動車や半導体の生産が大事だということはわかりますが
学生時代に社会科が苦手だった私にはどうにも見えてこないです。
確かにシルクは魅力がありますが…。
当たり前すぎることって調べても書いてないものですね。
生糸に代わる材料としてナイロンが開発されましたが
「NYLONを逆に読むとノーリン(農林省)」なんて
高校の先生が冗談を言っていたのを思い出してしまいました。
輸送はどうしていたのでしょうね。
六工社ができたのが1874(明治8)年
長野駅開業は1888(明治21)年
千曲川で運んでいたのでしょうか?
そうそう、製糸といえば、
当然こういう話題も関係してきますね。
「がむがゆく」 10月13日
Posted by sak 改め Saxan at 18:00│Comments(4)
│信州
この記事へのコメント
課題の提供ありがとうございます。
それぞれの課題に私見を述べたいところですが
あまり「知識を持ち合わせていないので
今回は輸送のことで
わかることを書かせていただきます。
六工社を立ち上げた一人、
大里忠一郎氏は
生産した生糸の輸送を円滑に行うために
鉄道建設に尽力しました。
その甲斐あって、
大正13年現在の長野電鉄線屋代須坂間開業し
屋代で国鉄とつながりました。
現在の松代駅は
その当時のままの建物だそうです。
なお六工社は日本で初めての民間機械製糸場ですので
もっと地元で顕彰する必要があると思っています。
それぞれの課題に私見を述べたいところですが
あまり「知識を持ち合わせていないので
今回は輸送のことで
わかることを書かせていただきます。
六工社を立ち上げた一人、
大里忠一郎氏は
生産した生糸の輸送を円滑に行うために
鉄道建設に尽力しました。
その甲斐あって、
大正13年現在の長野電鉄線屋代須坂間開業し
屋代で国鉄とつながりました。
現在の松代駅は
その当時のままの建物だそうです。
なお六工社は日本で初めての民間機械製糸場ですので
もっと地元で顕彰する必要があると思っています。
Posted by 遊学城下町信州松代 at 2007年10月18日 10:01
at 2007年10月18日 10:01
 at 2007年10月18日 10:01
at 2007年10月18日 10:01本日のブログで六工社関連のことを書かせていただいて
貴ブログをご紹介させていただきリンクをはらせていただきましたので
アクセスがあるかと思います。ごめいわくでしたらご連絡をお願いいたします。
いつも松代関連の話題を提供していただいて嬉しいです。
今後もよろしくおねがいいたします。
貴ブログをご紹介させていただきリンクをはらせていただきましたので
アクセスがあるかと思います。ごめいわくでしたらご連絡をお願いいたします。
いつも松代関連の話題を提供していただいて嬉しいです。
今後もよろしくおねがいいたします。
Posted by 遊学城下町信州松代 at 2007年10月18日 15:24
at 2007年10月18日 15:24
 at 2007年10月18日 15:24
at 2007年10月18日 15:24ご教示ありがとうございます。
またリンクもありがとうございます。
六工社と電鉄(当時は河東鉄道ですね)は
そういう繋がりがあったんですね。
ちょっとインターネットで調べてみましたが
「河東」という意味が本来はもっと壮大だったのを知り
また驚いてしまいました。
またリンクもありがとうございます。
六工社と電鉄(当時は河東鉄道ですね)は
そういう繋がりがあったんですね。
ちょっとインターネットで調べてみましたが
「河東」という意味が本来はもっと壮大だったのを知り
また驚いてしまいました。
Posted by sak at 2007年10月18日 22:52
いやいや
私のブログにつなげていただき
ありがとうございました。
さなぎ、また食したくなりました。
私のブログにつなげていただき
ありがとうございました。
さなぎ、また食したくなりました。
Posted by がむ at 2007年10月18日 23:40
at 2007年10月18日 23:40
 at 2007年10月18日 23:40
at 2007年10月18日 23:40