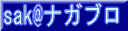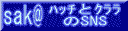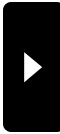お気に入りBlog新着
硫黄島からの手紙

WOWOWで「硫黄島からの手紙」をやっていました。
映画館でもDVDでも観たことがなく、今日が初めてでした。
精神論を唱え合理的な根拠もないのに
“万歳攻撃”だけが最善の方法と信じる人たちを
抑えようとする栗林中将のような姿は
日本が作ってきた映画では見られなかったように思います。
ある意味、淡々と作られた映画のように見えますが
このように作るのは難しいのでしょうね。
それにしても、クリント・イーストウッドは
何故この作品を作ろうと思ったのでしょうね。
片側ばかりの視点で見た戦争ものは
公平な見方ができない、と考えたのでしょうか。
そういうバランス感覚があったからこそかもしれませんね。
因みに「硫黄島」の読みは近隣住民の願いにより
今年「いおうとう」に決まったそうです。
また死の数日前3月17日時点で、
正式には「栗林大将」なのだそうです。
ご無沙汰してます。
だいぶご無沙汰してしまいました。
ちょっと余部まで旅行に行っていたので
その計画と実行と復習(ブログ書き)で何もできませんでした。
旅行で感じたのは、長野というところは今だけでなく
明治の頃も鉄道敷設などに力が入れられていたということ。
長野駅開業が明治21年、碓氷峠開通が明治26年
今回見てきた余部鉄橋は明治45年。
東京から日本海側へ抜けるための目的だったにしても
その恩恵は充分に受けてきたような気がします。
そして…2014年には金沢まで新幹線開通の予定。
長野は意外と恵まれた環境にあることを知るべきだと思いました。
ちょっと余部まで旅行に行っていたので
その計画と実行と復習(ブログ書き)で何もできませんでした。
旅行で感じたのは、長野というところは今だけでなく
明治の頃も鉄道敷設などに力が入れられていたということ。
長野駅開業が明治21年、碓氷峠開通が明治26年
今回見てきた余部鉄橋は明治45年。
東京から日本海側へ抜けるための目的だったにしても
その恩恵は充分に受けてきたような気がします。
そして…2014年には金沢まで新幹線開通の予定。
長野は意外と恵まれた環境にあることを知るべきだと思いました。
Posted by
sak 改め Saxan
at
20:09
│Comments(
2
)
松代大本営地下壕
今日の朝刊によれば、
きのう第16回新聞大会で松代周辺の視察があったそうです。
懐中電灯を片手に松代大本営地下壕も視察したそうです。
30年ほど前、私が小学生の頃、
なぜかそこは「ズリ」と呼ばれていました。
親たちは詳しく教えてくれなかったので
“秘密のスポット”みたいな所でした。
本来ズリとは土砂や礫のことですから
大人たちは開善寺経蔵の近くの「石山」を
想像して齟齬があったのかもしれません。
“長期休み中に行ってはいけない所”として
学校で確認する度に逆に興味は尽きませんでした。
「迷路のようになっていて出て来れなくなったり
落磐があるかもしれないから」との理由でした。
友人に場所を教えてもらったのは高学年の頃。
あの頃は人が入れないように
盛土してあったためだと思いますが、
入り口がとても狭くなっていて
怖くて私などは10m入っただけで断念。
今のような形に公開できているのは
篠ノ井旭高校(今の長野俊英高校)の生徒たちが
“タブー”に挑戦してくれたから。
きっと彼らの中に地下壕を探検しようとした
“悪ガキ”(誉め言葉です)がいたのでしょう。
歴史が風化するギリギリのところで彼らに救われました。
観光資源というより平和目的で活用してほしいと思います。
きのう第16回新聞大会で松代周辺の視察があったそうです。
懐中電灯を片手に松代大本営地下壕も視察したそうです。
30年ほど前、私が小学生の頃、
なぜかそこは「ズリ」と呼ばれていました。
親たちは詳しく教えてくれなかったので
“秘密のスポット”みたいな所でした。
本来ズリとは土砂や礫のことですから
大人たちは開善寺経蔵の近くの「石山」を
想像して齟齬があったのかもしれません。
“長期休み中に行ってはいけない所”として
学校で確認する度に逆に興味は尽きませんでした。
「迷路のようになっていて出て来れなくなったり
落磐があるかもしれないから」との理由でした。
友人に場所を教えてもらったのは高学年の頃。
あの頃は人が入れないように
盛土してあったためだと思いますが、
入り口がとても狭くなっていて
怖くて私などは10m入っただけで断念。
今のような形に公開できているのは
篠ノ井旭高校(今の長野俊英高校)の生徒たちが
“タブー”に挑戦してくれたから。
きっと彼らの中に地下壕を探検しようとした
“悪ガキ”(誉め言葉です)がいたのでしょう。
歴史が風化するギリギリのところで彼らに救われました。
観光資源というより平和目的で活用してほしいと思います。
六工社について考察
10月2日のブログを少しだけ考察(というか課題作りです)。
まず、六工社の立地条件について。
「富岡製糸場のあらまし」によれば
1.富岡付近は生糸を作るのに必要な繭が確保できるから。
2.工場建設に必要な広い土地が用意できるから。
3.製糸に必要な水の確保ができるから(鏑川、高田川)。
4.燃料(ねんりょう)の石炭が近くの高崎で採れるから。
5.地元の人たちの協力が得られたから。
が官営工場を富岡に立地した条件だったようですが、
これと比べてみたいと思います。
1.私が生まれた頃も養蚕は残っていました(気象条件がカギ?)。
2.民営だから狭くてもOK?
3.神田川の目の前ですね(水は足りたのかな?)。
4.もしかして山の木を切ってきた???
5.外国人は来ないから関係ないのかな?
疑問符だらけになってしまいました。
色々と調べていたら、pdfファイルが見つかりました。
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/riim/img/img_res/WPNo.19_imai.pdf
ふと思ったのですが、なぜ明治時代には
日本からあんなに生糸が輸出されたのでしょうね。
輸入した国は生糸で何を作ったんでしょう?
今の時代に生きていれば、
自動車や半導体の生産が大事だということはわかりますが
学生時代に社会科が苦手だった私にはどうにも見えてこないです。
確かにシルクは魅力がありますが…。
当たり前すぎることって調べても書いてないものですね。
生糸に代わる材料としてナイロンが開発されましたが
「NYLONを逆に読むとノーリン(農林省)」なんて
高校の先生が冗談を言っていたのを思い出してしまいました。
輸送はどうしていたのでしょうね。
六工社ができたのが1874(明治8)年
長野駅開業は1888(明治21)年
千曲川で運んでいたのでしょうか?
そうそう、製糸といえば、
当然こういう話題も関係してきますね。
「がむがゆく」 10月13日
まず、六工社の立地条件について。
「富岡製糸場のあらまし」によれば
1.富岡付近は生糸を作るのに必要な繭が確保できるから。
2.工場建設に必要な広い土地が用意できるから。
3.製糸に必要な水の確保ができるから(鏑川、高田川)。
4.燃料(ねんりょう)の石炭が近くの高崎で採れるから。
5.地元の人たちの協力が得られたから。
が官営工場を富岡に立地した条件だったようですが、
これと比べてみたいと思います。
1.私が生まれた頃も養蚕は残っていました(気象条件がカギ?)。
2.民営だから狭くてもOK?
3.神田川の目の前ですね(水は足りたのかな?)。
4.もしかして山の木を切ってきた???
5.外国人は来ないから関係ないのかな?
疑問符だらけになってしまいました。
色々と調べていたら、pdfファイルが見つかりました。
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/riim/img/img_res/WPNo.19_imai.pdf
ふと思ったのですが、なぜ明治時代には
日本からあんなに生糸が輸出されたのでしょうね。
輸入した国は生糸で何を作ったんでしょう?
今の時代に生きていれば、
自動車や半導体の生産が大事だということはわかりますが
学生時代に社会科が苦手だった私にはどうにも見えてこないです。
確かにシルクは魅力がありますが…。
当たり前すぎることって調べても書いてないものですね。
生糸に代わる材料としてナイロンが開発されましたが
「NYLONを逆に読むとノーリン(農林省)」なんて
高校の先生が冗談を言っていたのを思い出してしまいました。
輸送はどうしていたのでしょうね。
六工社ができたのが1874(明治8)年
長野駅開業は1888(明治21)年
千曲川で運んでいたのでしょうか?
そうそう、製糸といえば、
当然こういう話題も関係してきますね。
「がむがゆく」 10月13日
信州人の気質(昨日のコメントの返事に代えて)
昨日のブログにコメントをいただいて思ったのですが
松代というのは“○○発祥の地”が多いですね。
最近のブログ(私以外のブログも含む)のネタだけでも、
電信,民間製糸工場,エノキ茸栽培,…と地味では
ありますが、時代を見越していると思います。
#電信なんて時代を先取りしすぎてますね。
松代は10万石と信州の中で最大の藩ですが
反面、豊かな土地とは言えないと思いますから
「生きるのに必死だったから」という理屈も
解らないでもないですが、それだけなら
他の地域の真似でも良かったような気がします。
脳学者の養老猛司が「バカの壁」で「個性とは
最初から生かそうとするものでなく、競い合った末に
出てくるもの」みたいなことを書いていましたが、
町についても言えるのかもしれませんね。
クリエイティブな人が信州に移り住んでくるのも
何かあるのかもしれませんね。
松代には進取の気風に富んだ人が多いのかもしれません。
信越線が松代に通らなかった話(「蒸気機関車のような
煙を吐く物は松代には要らん」と偉い人が言ったとか)
などを聞くと、疑問を持ってしまう面もありますが…。
先週からテレビ信州で「秘密の県民ショー」という
番組が始まりましたが、なかなか興味深いです。
以前にスペシャルで2回ほど放送された時は
「皆が県歌を歌える県」「中学で3000m級の山に登る」
「学校では掃除の時間は私語禁止」など
番組関係者の中に長野県出身者がいるのではないかと
思えるほど、よく長野が“いじられ”ています
(先週は駒ヶ根IC近くにある「女体入口」という
バス停を取り上げていました)。
某コーヒー店の初日入店数が世界記録になったとか
ナガブロが短期間で1000を超えたとか
もちろん関係者の方々の尽力もありますが、
こういう事象を分析すると県民性が理解できるのかも。
芸能人が少ないのも特徴のように思います。
乙葉を長野県向けのCMに出すのは大正解だと思います。
政治家が少ない一方で司法関係者が多いとも聞きます。
親子で内閣総理大臣は今回が初めてだそうですが
最高裁判所長官はだいぶ昔に2代続けて
横田家が就任しています(父親は大審院長ですが)。
松代というのは“○○発祥の地”が多いですね。
最近のブログ(私以外のブログも含む)のネタだけでも、
電信,民間製糸工場,エノキ茸栽培,…と地味では
ありますが、時代を見越していると思います。
#電信なんて時代を先取りしすぎてますね。
松代は10万石と信州の中で最大の藩ですが
反面、豊かな土地とは言えないと思いますから
「生きるのに必死だったから」という理屈も
解らないでもないですが、それだけなら
他の地域の真似でも良かったような気がします。
脳学者の養老猛司が「バカの壁」で「個性とは
最初から生かそうとするものでなく、競い合った末に
出てくるもの」みたいなことを書いていましたが、
町についても言えるのかもしれませんね。
クリエイティブな人が信州に移り住んでくるのも
何かあるのかもしれませんね。
松代には進取の気風に富んだ人が多いのかもしれません。
信越線が松代に通らなかった話(「蒸気機関車のような
煙を吐く物は松代には要らん」と偉い人が言ったとか)
などを聞くと、疑問を持ってしまう面もありますが…。
先週からテレビ信州で「秘密の県民ショー」という
番組が始まりましたが、なかなか興味深いです。
以前にスペシャルで2回ほど放送された時は
「皆が県歌を歌える県」「中学で3000m級の山に登る」
「学校では掃除の時間は私語禁止」など
番組関係者の中に長野県出身者がいるのではないかと
思えるほど、よく長野が“いじられ”ています
(先週は駒ヶ根IC近くにある「女体入口」という
バス停を取り上げていました)。
某コーヒー店の初日入店数が世界記録になったとか
ナガブロが短期間で1000を超えたとか
もちろん関係者の方々の尽力もありますが、
こういう事象を分析すると県民性が理解できるのかも。
芸能人が少ないのも特徴のように思います。
乙葉を長野県向けのCMに出すのは大正解だと思います。
政治家が少ない一方で司法関係者が多いとも聞きます。
親子で内閣総理大臣は今回が初めてだそうですが
最高裁判所長官はだいぶ昔に2代続けて
横田家が就任しています(父親は大審院長ですが)。
エノキダケ
本当は信州全般にまで歴史の勉強範囲を広げたいのですが
なかなか調べている時間がなく、
今回も松代関係の既知の知識です。
私が中学生のときに理科の先生から
エノキダケの人工栽培を始めたのは
旧制中学の先生だった長谷川五作という
松代の方だということを聞きました。
詳しくはこちら(wikipedia)
大正12年のことですから、ちょっと「歴史」とは言えないかも。
今では長野IC近くの道路で「発祥の人」と書かれたものが
立っていますが当時は全く知らないことで驚きました。
#それにしても「エノキ茸発祥の地」っておかしくないですか?
#「エノキ茸栽培発祥の地」とすべきかと…。
不思議なのは、昔の先生は今とは違うとは言っても
大学でもない学校の先生が栽培法をご存知だったことです。
長谷川五作がどんな経歴をお持ちなのか興味が湧きます。
余談ですが、シイタケ栽培は1942年に現在の方法を
森喜作(こちらは群馬の方)が編み出すまでは
菌糸がつくかどうかは運に頼らざるをえず命がけだったとか
(昭和30年代の教科書に載ったそうです。
マンガ「美味しんぼ」にも載っていますね)。
今では珍重されるのはマツタケくらいですが
昔は色々なキノコが貴重だったんでしょうね。
そろそろキノコのシーズンですが感謝して食べねば。
なかなか調べている時間がなく、
今回も松代関係の既知の知識です。
私が中学生のときに理科の先生から
エノキダケの人工栽培を始めたのは
旧制中学の先生だった長谷川五作という
松代の方だということを聞きました。
詳しくはこちら(wikipedia)
大正12年のことですから、ちょっと「歴史」とは言えないかも。
今では長野IC近くの道路で「発祥の人」と書かれたものが
立っていますが当時は全く知らないことで驚きました。
#それにしても「エノキ茸発祥の地」っておかしくないですか?
#「エノキ茸栽培発祥の地」とすべきかと…。
不思議なのは、昔の先生は今とは違うとは言っても
大学でもない学校の先生が栽培法をご存知だったことです。
長谷川五作がどんな経歴をお持ちなのか興味が湧きます。
余談ですが、シイタケ栽培は1942年に現在の方法を
森喜作(こちらは群馬の方)が編み出すまでは
菌糸がつくかどうかは運に頼らざるをえず命がけだったとか
(昭和30年代の教科書に載ったそうです。
マンガ「美味しんぼ」にも載っていますね)。
今では珍重されるのはマツタケくらいですが
昔は色々なキノコが貴重だったんでしょうね。
そろそろキノコのシーズンですが感謝して食べねば。
Posted by
sak 改め Saxan
at
23:57
│Comments(
2
)
wikipediaに投稿しませんか?
wikipediaをご存知ですか?
誰もが投稿・修正などができるオープンな百科事典です。
“誰もが”という点で正確さ等に欠ける
可能性が高いため嫌がる人もいますが
以前より多くの人が活用していると思います。
インターネットで検索してwikipediaが引っかかったら
私はまずwokipediaに訪れることが多いです。
逆にwikipediaが引っかからない場合は
「この調査は苦労するかも…」と思うことが多いです。
例えば「六工社」「和田英」などは検索に引っかかりません。
また、記述が詳しくないものも散見されます。
「富岡製糸場」に「富岡日記」へのリンクはあるものの
「横田英」という名前も見当たりません。
ということで、我々が知っていることを
こういう所に書き込んでいくのも
1つの方法なのではないかと思いました
(知識が無くてもレイアウトを構成するのが上手い人、
構成に長けている人など色々な方の力が必要です)。
とりあえず、いくつか作ってみました。
時間も史料も手許に無いため、ごくごく簡単にですが…。
是非とも皆様に加筆・修正していただきたいと思います。
誰もが投稿・修正などができるオープンな百科事典です。
“誰もが”という点で正確さ等に欠ける
可能性が高いため嫌がる人もいますが
以前より多くの人が活用していると思います。
インターネットで検索してwikipediaが引っかかったら
私はまずwokipediaに訪れることが多いです。
逆にwikipediaが引っかからない場合は
「この調査は苦労するかも…」と思うことが多いです。
例えば「六工社」「和田英」などは検索に引っかかりません。
また、記述が詳しくないものも散見されます。
「富岡製糸場」に「富岡日記」へのリンクはあるものの
「横田英」という名前も見当たりません。
ということで、我々が知っていることを
こういう所に書き込んでいくのも
1つの方法なのではないかと思いました
(知識が無くてもレイアウトを構成するのが上手い人、
構成に長けている人など色々な方の力が必要です)。
とりあえず、いくつか作ってみました。
時間も史料も手許に無いため、ごくごく簡単にですが…。
是非とも皆様に加筆・修正していただきたいと思います。
Posted by
sak 改め Saxan
at
23:52
│Comments(
3
)
板垣信方・屋代源吾の墓
「風林火山」でも扱われた「上田原の戦い」
家臣の墓に行ってきました。
先ずは武田家の家臣である板垣信方の墓(地図はこちら)。
NHK「風林火山」では千葉真一が演じていました。

神社になっているんですね。
赤い鳥居をくぐって少し歩くと小さな祠が見えてきます。

タバコが好きだったとのことで、タバコが供えられていました。

車で少し進むと(歩いていける距離ですが)
屋代源吾基綱の(のものと伝えられている)墓。
こちらは村上義清の家臣。

千曲市に屋代という地名がありますが
関係あるんでしょうかねぇ。
「風林火山」には長野氏も出てましたね。
家臣の墓に行ってきました。
先ずは武田家の家臣である板垣信方の墓(地図はこちら)。
NHK「風林火山」では千葉真一が演じていました。
神社になっているんですね。
赤い鳥居をくぐって少し歩くと小さな祠が見えてきます。
タバコが好きだったとのことで、タバコが供えられていました。
車で少し進むと(歩いていける距離ですが)
屋代源吾基綱の(のものと伝えられている)墓。
こちらは村上義清の家臣。
千曲市に屋代という地名がありますが
関係あるんでしょうかねぇ。
「風林火山」には長野氏も出てましたね。
小諸義塾
あるイベントのために小諸に行きました。
小諸駅と懐古園の間に、小諸義塾の碑がありました。

小諸義塾は1893(明治26)年11月~1906(明治39)年3月と
開校していた期間は短いように思えますが
島崎藤村が1899(明治32)年から6年間教えていました。
小諸駅開業が1888(明治21)年12月、
横川-軽井沢間開業が1893(明治26)年4月ですから(関連記事はこちら)
既に義塾の前を小諸駅に上野行きの列車が通っていたことになりますね。
小諸駅と懐古園の間に、小諸義塾の碑がありました。
小諸義塾は1893(明治26)年11月~1906(明治39)年3月と
開校していた期間は短いように思えますが
島崎藤村が1899(明治32)年から6年間教えていました。
小諸駅開業が1888(明治21)年12月、
横川-軽井沢間開業が1893(明治26)年4月ですから(関連記事はこちら)
既に義塾の前を小諸駅に上野行きの列車が通っていたことになりますね。
国名「信濃」part1(Re:泰輝さんの発問)
10月3日のコメント欄で泰輝さんが言われたこと
について、今日は考える第一歩としたいと思います。
まず「信州」については
武蔵→武州
上野→上州
長門→長州
となることからも
信濃→信州
であることは想像がつきます。
ただし、どういう国名に「州」が付くのかは今後の課題。
問題は「信濃」のほうだと思います。
「科野」が転じたという話は聞いたことがありますが
その辺が手掛かりになりそうです。
科野と呼ばれていた時代の中央官庁は
今の千曲市にあったそうですが、
その千曲市にある「科野の里」内の長野県立歴史館
に行ってみる必要はあるかもしれません。
ちょっと気になっているのは
明科、豊科など「科」の付く地名が多い中で
「更級郡」については「しな」が「級」であること。
これも今後の課題です。
課題ばかりで、けっきょく何の結論も出ていませんが
今回は第一歩ということで…。
について、今日は考える第一歩としたいと思います。
まず「信州」については
武蔵→武州
上野→上州
長門→長州
となることからも
信濃→信州
であることは想像がつきます。
ただし、どういう国名に「州」が付くのかは今後の課題。
問題は「信濃」のほうだと思います。
「科野」が転じたという話は聞いたことがありますが
その辺が手掛かりになりそうです。
科野と呼ばれていた時代の中央官庁は
今の千曲市にあったそうですが、
その千曲市にある「科野の里」内の長野県立歴史館
に行ってみる必要はあるかもしれません。
ちょっと気になっているのは
明科、豊科など「科」の付く地名が多い中で
「更級郡」については「しな」が「級」であること。
これも今後の課題です。
課題ばかりで、けっきょく何の結論も出ていませんが
今回は第一歩ということで…。